一般的に夫の年収が1,000万円以上と聞くと、どんなイメージをお持ちですか?

高収入で羨ましい!タワマンに住めるかも?
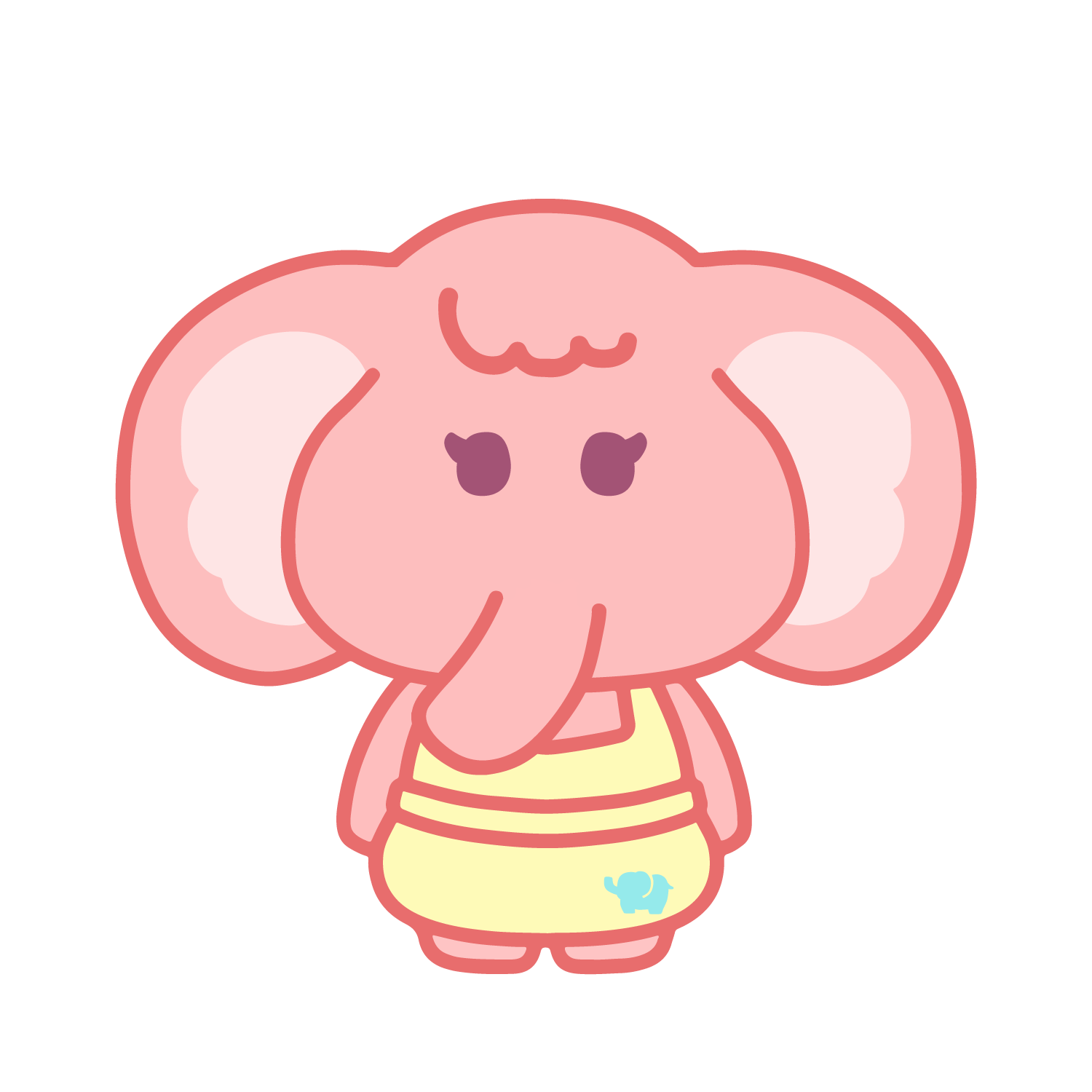
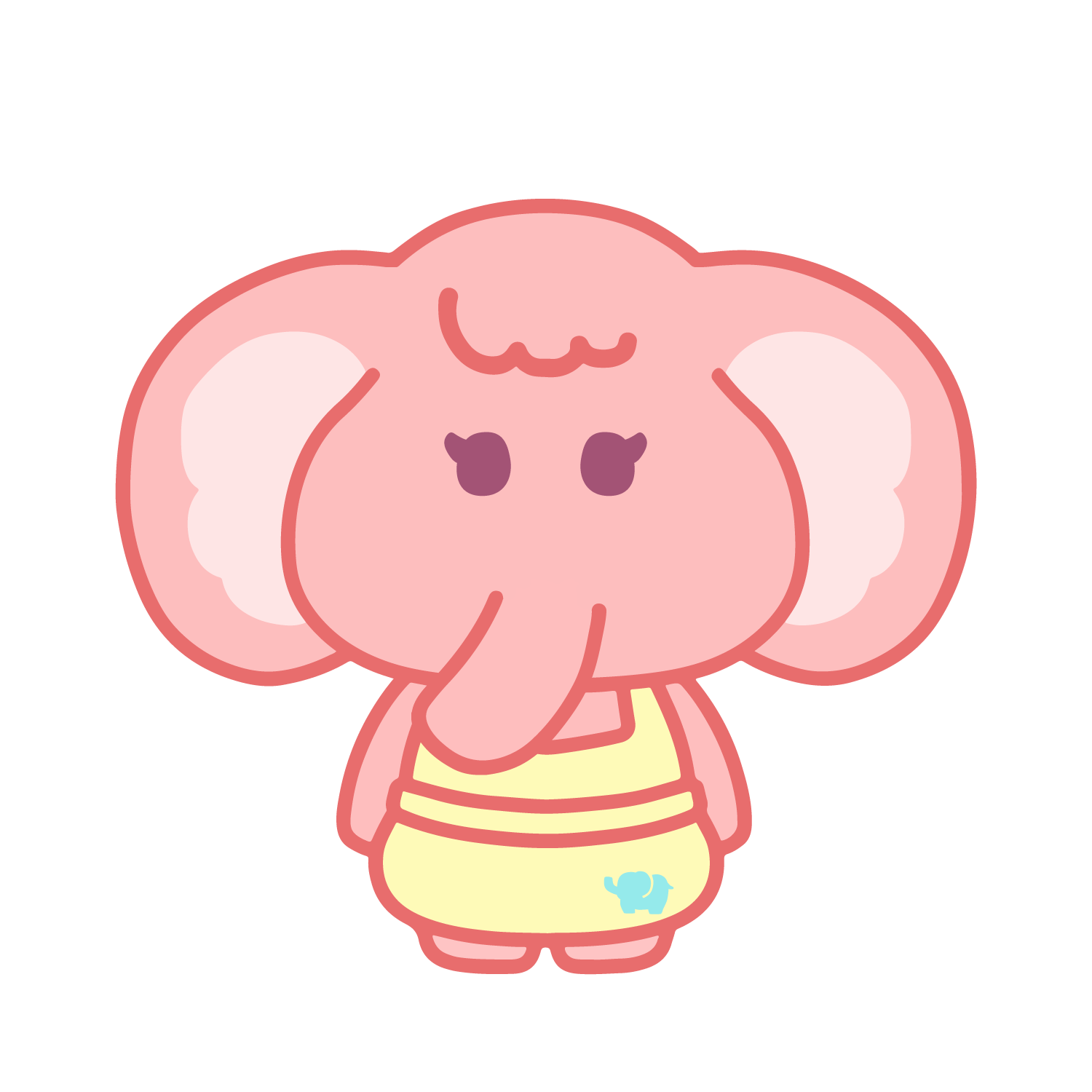
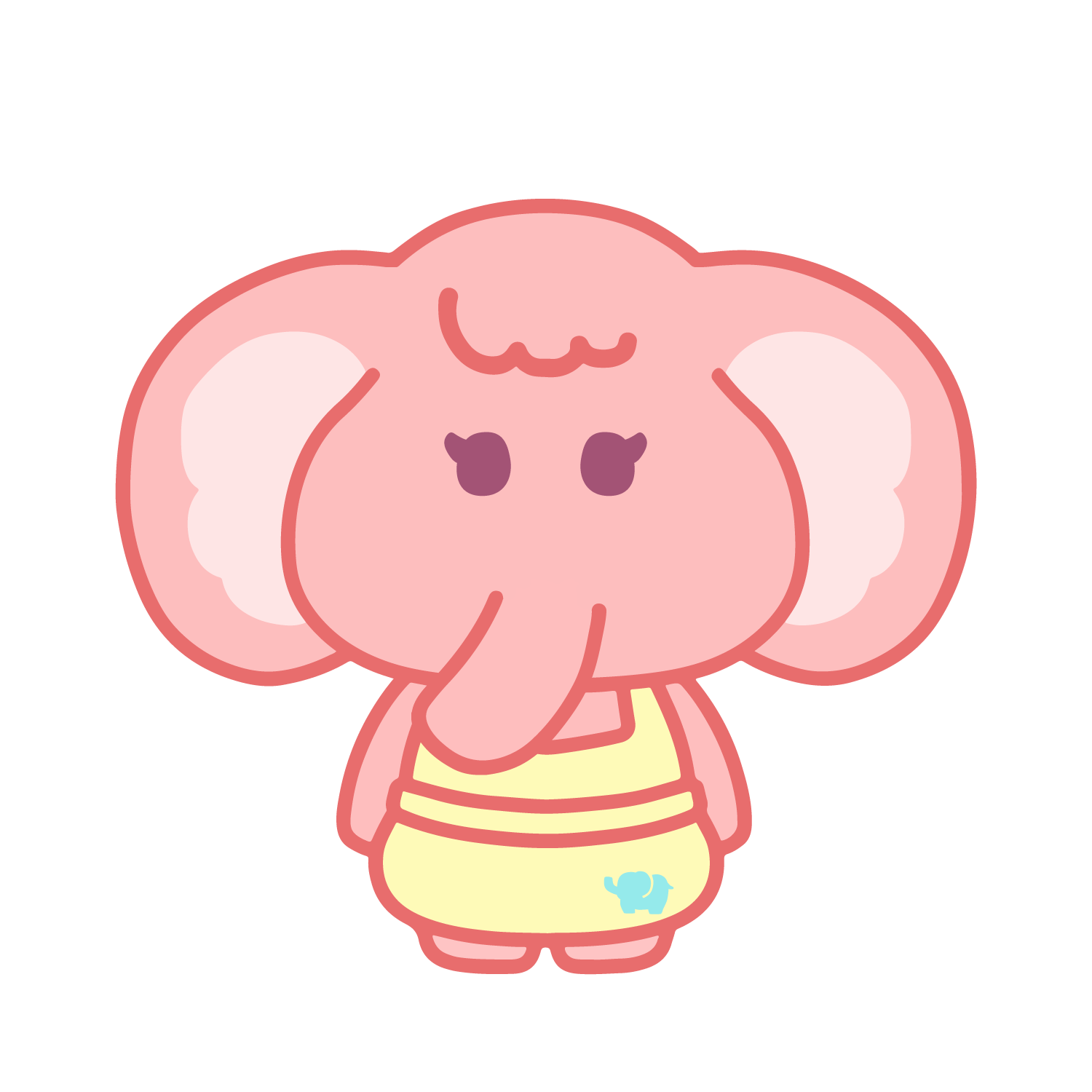
玉の輿でいいなぁ



うちの夫もそのぐらい稼いでくれたら・・・。
このように、「羨ましい・贅沢できそう」などいわゆる「お金持ちな家庭」と思う人は多いのではないでしょうか?
一方、年収1000万円以上ある夫と結婚しても、思ったより生活が豊かでなかったという声もよく耳にします。
本記事では、年収1,000万円以上の夫を持つ妻の本音を知り、落とし穴ともいえるデメリットについて解説します。
また、高年収夫と結婚した場合の妻の働き方についてもお話ししていきますのでぜひ参考にしてください。
日本人全体の5%!?年収1,000万円以上の割合とは
そもそも、年間の給与が1,000万円を超えるような高所得の人は、日本にはどのくらいいるのでしょうか?
国税庁の民間給与実態統計調査では、年間給与1,000万円以上の人は、日本の給与所得者のうち、全体で約5%となっています。


上記の表は、国税庁が告知している年収の割合を表にまとめたものです。
また、2022年最新のデータによると、日本全体の平均給与は443万円です。
男女別内訳をみても、男性545万円、女性302万となっており、平均給与からみても、やはり年収1,000万円以上の人は高所得に分類されることは間違いなさそうです。


年収1,000万円以上の夫は羨ましい?妻たちの本音


年収1,000万円を超える日本人は全体の5%しかいないため、高所得といえるでしょう。
このように余裕のある生活を送れるとイメージしがちですが、ネット上では年収1,000万円以上の夫を持つ妻たちが「経済的に楽ではない」と意外な本音よく見受けられます。
マイホームを購入後、経済的な理由で手放す人は何割くらいいますか?
当方、夫婦ともに34歳、子供3人、専業主婦で夫の年収は1000万です。
年収一千万とは言え、夫の奨学金や年金の 猶予の繰り下げ返済等で、 生活は苦しいです。当然、賃貸暮らしですが、息子たちの同級生家族を見ると、失礼ながらうちより年収の低い方が当然のようにマイホームを購入されています。 先日、新聞で読みましたがマイホーム購入には頭金一千万必要との事。
本当にみなさん二十代で一千万も貯金できてるのでしょうか?
このカテで、さきほど購入してはみたもののローンが払えず、家を手放す方たちもいると知って、驚きました。
マイホームを購入後、きちんど維持できている人たちって、どのくらいいるのでしょうか?正直、マイホームがうらやましいです。
yahoo知恵袋
【支給】「年収1000万円の所得制限」 リッチな生活を送れるとイメージされがちです。
しかし子育て世帯では、それほど裕福には暮らせないのが実情。
独身や子なし夫婦に比べて、人数が多いので生活費が多く必要になったり、子どもに教育費がかかったりするということ。それだけでなく、年収1000万円を超えると「所得制限」のため、あらゆる子育て支援策を受けれません。
しかし、所得制限のかからない方々に生活が苦しいと伝えても、◯どこか出費しすぎ
yahoo知恵袋
◯贅沢な生活してるから
と言って理解されません。 なぜでしょうか?
これらの声を見てみると、それぞれの家庭により事情や環境が異なるため一概には言えません。
しかし、年収1,000万円以上だから余裕のある生活を送れるとは限らなさそうです。
とはいえ、年収1000万円は、一般的に高所得者と呼ばれる分類に該当します。
なぜ年収1,000万円以上の夫を持つ妻が、経済的に苦しいと感じてしまうのでしょうか?
ここからは、年収が1,000万円を超える世帯の実態を解明していきます!
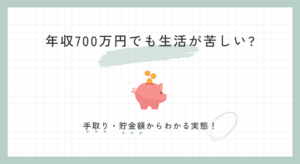
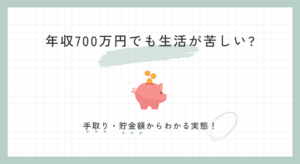
夫の年収が1,000万あると手取りはいくら?


そもそも、額面で年収が1000万円ある場合、月々の手取りはどの程度となるのでしょうか?
実際に家計として使えるお金について確認していきましょう。
手取りはいくら?年収1,000万円の実態とは?
夫の年収が1,000万円以上と聞くと、ついつい高収入というイメージを持ってしまいますが、1,000万円すべてが手取りとして得られるわけではありません。
額面である1,000万円から、所得税や住民税などの税金や、各種保険料などが引かれます。
最終的に残った金額が実際の収入、つまり「手取り金額」になります。
それでは実際に年収1,000万円の世帯では、一体どのぐらい税金がひかれ、手取り金額はいくらなのでしょうか?
年収1,000万円の手取りの目安は以下の通りになります。
雇用形態や住んでいる地域、扶養人数、加入している保険などさまざまな要因によって支払う税金は異なります。
あくまでも目安として参考にしてください。
【給与から引かれるもの】
| 税金・各種保険料 | 税率 |
|---|---|
| 所得税(900万円以上1800万円以下の場合) | 税率約33% |
| 住民税 | 都道府県に4%・市町村に6% |
| 社会保険料 | 給料の約15% |
| 雇用保険料 | 給料の約0.3% |
額面である1,000万円から約300万円が税金として引かれることになり、手元に残る手取り金額は約700万円になります。
実際に手元に残る金額は思っていたより少ないと感じる人も多いでしょう。
さらに上記の金額から、奨学金の返済や子供の教育費、住宅ローンや家賃、車のローン、任意保険など様々な出費があります。
これらを差し引くと、全く贅沢ができないケースも少なくありません。
このように、年収1,000万円と聞くと、1,000万円すべてが使えるお金であると考えてしまいがちですが、実際はかなりの額が税金でひかれてしまうのです。
なぜ?年収1,000万円を超えても家計のやりくりが苦しいと思う理由
年収1,000万円以上の夫を持つ妻が、家計のやりくりが苦しいと感じてしまうのはなぜでしょうか?
考えられる理由のひとつとして、日本の税制度上、手取り金額が増えにくいことがあげられるでしょう。
日本では、累進課税制度が採用されているため、収入が高くなるほど、支払わなければならない税金の割合も高くなります。
つまり年収が増えても、実際の手取り金額は増えにくいのです。
このような理由から、年収が1,000万円以上の夫であっても、妻は家計のやりくりが苦しいと感じてしまう状況が生まれてしまうのでしょう。
都市部の平均年収は高い?物価が高い都市部は出費も多くなる傾向に…
一般的に、都市部で働く人の平均年収は、地方で働く人に比べて高い傾向があります。
しかし、地方と比較すると物価が高い都市部では出費も多くなるため、年収が高いからといって必ずしも豊かな生活を送れるわけではありません。
とくに、東京などの大都市では住居費や駐車場代、外食費、食料品が高く、家計の負担が大きくなる要因と言えます。
仮に家族3人で(2LDK、2K、2DK)ぐらいの大きさの物件に住もうと思うと東京都内の平均家賃は以下の通りとなります。
| 東京23区内 | 平均家賃 |
|---|---|
| 千代田区 | 20,44万円 |
| 港区 | 23.53万円 |
| 新宿区 | 18.56万円 |
| 文京区 | 17.18万円 |
| 渋谷区 | 22.83万円 |
| 中央区 | 19.00万円 |
都市部の生活では、特別贅沢しているつもりがなくても、家計のやりくりが苦しくなる可能性が高いのです。
意外な落とし穴⁈夫の年収1,000万円以上で考えられる5つのデメリット
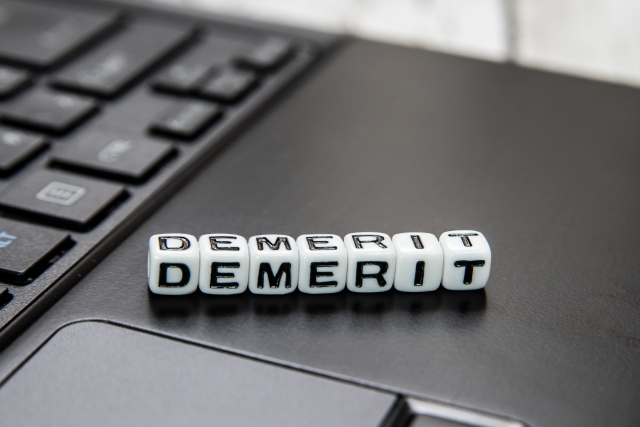
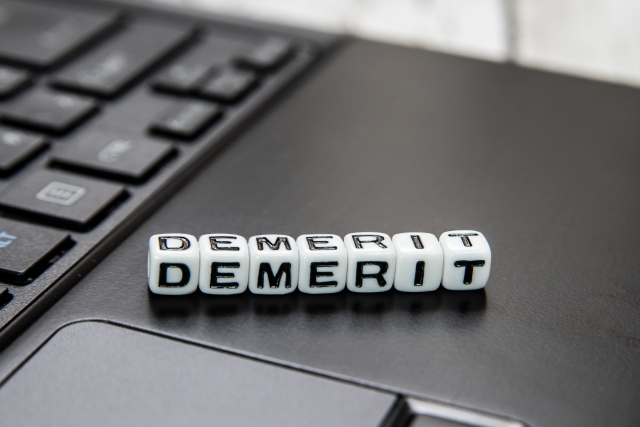
夫が年収1,000万円以上と聞くと、ついつい羨ましいと感じてしまいがちですが、落とし穴ともいえる意外なデメリットもあるので注意が必要です。
ネット上でも、税制上の問題がわからく困っている人の声が投稿されています。
ここからは、代表的な5つのデメリットをそれぞれ詳しく解説していきます。
夫の年収1,000万円以上のデメリット①:
児童手当が支給されない可能性あり
夫の年収が1,000万円以上だと、児童手当が支給されない可能性があります。
児童手当を受給するには、所得制限をクリアしなければなりません。
児童手当とは、子育て世帯を支援するための手当です。
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している一定所得以下の世帯に支払われます。手当額は、満額で受け取れる世帯の場合、3歳未満が月1万5,000円、3歳以上小学生までが月1万円(第3子以降は1万5,000円)、中学生は一律月1万円となっています。
児童手当制度のご案内
夫の収入が定められた所得制限限度額を超えている場合、支給額が一律毎月5,000円に減額または支給対象外(2022年10月から)とされてしまいます。
扶養している子どもの人数や妻の収入等により所得制限限度額は変わってきますが、年収が1,000万円を超える場合、児童手当は支給されない可能性が高いでしょう。
夫の年収1,000万円以上のデメリット②:
社会保険料の引き上げ
社会保険料とは、5つの社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)にかかる保険料のことです。
なお、介護保険料は40歳以上が対象となります。
社会保険料は年収に応じて金額が決められる累進課税制度です。
つまり収入が増えれば増えるだけ、社会保険料も引き上げられます。
社会保険料は賞与の有無や支給金額、職業や職種によって金額は変わり、高額になると、年間で150万円を超える場合もあります
たとえ1,000万円以上稼いでも、支払う額が多ければ、家計への負担は大きくなるでしょう。
夫の年収1,000万円以上のデメリット③:
給与所得控除が減る
給与所得控除とは、所得税計算の基盤となる給与所得額を確定させるために、1年間の給与などの収入額に応じて差し引かれる控除のことです。
自営業者などの事業所得者は、所得税を算出する際、収入から交際費や外注費などといった必要経費を差し引きます。
一方、サラリーマンなど給与所得者には、収入から経費を差し引く制度がありません。
そのため、給与収入に応じて差し引かれるのが「給与所得控除」になります。
給与所得控除額は、収入が増えれば増えるほど減らされてしまいます。
控除額が減ることは、手取り金額が少なくなることですから、家計への負担は増えるでしょう。
なお、給与所得控除の金額は年収が850万円を超えると、一律195万円となります。
夫の年収1,000万円以上のデメリット④:
配偶者控除が受けられない
配偶者控除制度は、以前は一律38万円の支給でした。
しかし、2020年に改正され、納税者本人の所得金額に応じて配偶者控除額が引き下げられました。
900万円以下はこれまでと変わりありませんが、年収1,000万円の人が該当するであろう「950万円から1,000万円以下」の場合には、これまでより25万円も少ない13万円となります。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
年間所得が1,000万円(給与収入のみの場合は1,195万円)を超えると、配偶者の収入額にかかわらず控除が受けられなくなります。
夫の年収1,000万円以上のデメリット⑤:
高等学校等就学支援金制度が受けられない
高等学校等就学支援金制度は高校の授業料に充てるお金を、国が支給してくれる制度です。
所得要件によって、支給額は11万8000円か39万6000円のどちらかになりますが、支給の対象は原則として年収の目安が910万円未満の世帯です。
夫の年収が1,000万円の家庭の場合、残念ながらどちらの支給も対象外となります。
年収1,000万円以上の夫を持つ妻の3つの働き方とは?


年収1,000万円以上の夫を持つ妻は、悠々自適な生活を送っているのでしょうか?
今までお話ししてきたように、家計のやりくりが大変な面もあるため、正社員やパートなどで働いている妻も多いようです。
ここからは、正社員で共働きの場合やパートで働いている場合、専業主婦の場合のそれぞれの生活におけるメリットとデメリットを紹介します。
妻の働き方その①:正社員で共働き
より多くの収入を得られるが支出も多い傾向に
夫の年収が1,000万円以上でも、正社員で共働きしている妻もいるでしょう。
妻も正社員で働いていれば、当然、世帯年収はさらに多くなります。
共働きの一番のメリットは、より多くの収入を得られることで裕福な生活ができるということです。
しかし、夫婦ともに正社員として働くことは、時間に余裕がなくなるというデメリットもあります。
そのため、仕事と家事の両立が難しいと感じる人も多いでしょう。
小さな子どもがいる家庭では、育児や子どもの送迎なども加わり、さらに時間的余裕がなくなるでしょう。
家事や育児を家事代行業者やベビーシッターなどに依頼することで、支出が多くなる傾向があります。
妻の働き方その②:パートで働く
配偶者控除を受け、夫の扶養範囲内で働く
年収1,000万円以上の世帯でも、家計のやりくりが大変に感じられる場合は、少しでも家計の助けになるようにパートで働く妻もいます。
妻の年収が103万円以下であれば、配偶者控除を受けられるため、扶養の範囲内で働く妻もいます。
ただし、配偶者控除は、納税者本人の年収によって控除額が段階的に変わり、年間所得が1,000万円(給与収入のみの場合は1,195万円)を超えると、配偶者の収入額にかかわらず控除が受けられなくなります。
年収1,000万円世帯にとってはギリギリのラインになるため配慮が必要です。
また、夫の年収で家計がやりくりできており、特に家計に不満を感じていなくても、働くのが好きという妻も少なくないでしょう。
家でじっとしているよりも外で働いて、自分のおこづかいをパートで稼ぐというのもひとつの方法です。
働き方その③:専業主婦
大切な家族のために時間を使える反面、孤独感も…
家にいるのが苦でない女性であれば、専業主婦に憧れる人も多いでしょう。
専業主婦の場合、自分の思い通りに家事や育児に時間をかけられることがメリットです。
妻や母として、大切な夫や幼い子どもの世話をすることは、とてもやりがいがあります。
ただし、社会とのつながりがない分、孤独を感じやすいという一面もあります。
また、ひとことで家事と言っても、さまざま仕事が無数にあるためキリがなく、なかなか達成感や満足感を感じられないという人もいるでしょう。
まとめ
年収1,000万円以上の人は、日本の給与所得者のうち5%しかいないため高所得者と言えるでしょう。
しかし、1,000万円は額面であり手取り金額ではありません。
額面から税金や保険料などが差し引かれた金額が、実際の手取り金額になります。
また、児童手当や高等学校等就学支援金制度などが受けられなかったり、社会保険料が引き上げられるなど、税制面でも多くのデメリットがあります。
そのため、家計のやりくりが大変と感じる妻がいるのも現実です。
年収1,000万円以上の夫を持つ妻の働き方は、正社員やパートで働く、もしくは専業主婦の3つのパターンがあります。
なかでも、夫の扶養内でパートなどで働く場合は要注意です。
夫の年間所得が1,000万円(給与収入のみの場合は1,195万円)を超えると、配偶者控除が受けられなくなるため、年収1,000万円世帯にとってはギリギリのラインであり配慮が必要となります。
どの働き方にもメリットとデメリットがあります。当然、家庭により考え方や事情が異なりますので、それぞれのライフステージに合わせて最適な働き方を選ぶようにしましょう。







